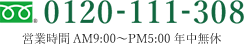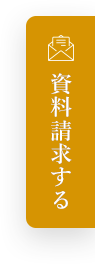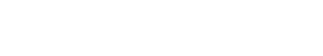すてきな世界のお墓まいりあれこれ
日本では、お墓まいりと言えば、春秋彼岸、お盆、月命日、回忌法要、お祝い事や悩みがある時等々、人生の節目の報告の意味もありました。いのちの大切さを識る良い機会です。

しかし、何と言っても春秋彼岸は、そのシーズンの頂点とも言えます。春分、秋分の、昼夜が同じ時間となる時期、彼岸(あの世)と此岸(この世)がある中で、喪くなった方が彼岸に行けるように墓参し供養するのです。死者を想い供養する「彼岸会」は、お中日をはさんで一週間の期間です。日本人は、何んと死者を想うやさしい民族でしょうか。お花とお線香を手向け祈ると心が落ち着きます。
この死者と生者の語り合う空間、お墓まいりの季節は、世界で様々です。キリスト教(カトリック)の国々では、11月1日の「死者の日」(万霊節)におまいりします。台湾では、4月初旬清明節のお墓まいりの日(掃苔)に家族でお墓を掃除して、花と線香を手向け、爆竹を鳴らします。
イタリアの墓地の周辺には、花屋さんが色とりどりの切花を売っています。菊が墓参の花でもあります。墓石には、陶板に写真を焼付けたものを接着するものがあります。愛する故人を、想い出すと共に、「お祖父さんが死後生まれた孫に祖父の顔を教えるため」と、墓参の白髪の美しい女性から聞きました。しかし、毎日のように墓参している彼女は、きっと愛する夫の写真(陶板の)に、キスをしているはずです。
ドイツや、オーストリア等の公営墓地、例えばウィーンの中央霊地の周辺には、50円~200円程度のプランターの花々が売られています。墓地には、じょうろが置かれ、毎日のように、墓地のガーデニングを楽しみ、花に水をやって、故人との対話をしています。
世界遺産となった、建築家アスプルンドの設計したスウェーデンの森林墓地は、樹木葬ではなく、かわいらしい墓石と墓参の方々のローソクの灯が輝く光景が、長い年月で植林した木々が森となり、この間に見える風景が、正に天国のような所でした。お墓は、本当におまいりして完成するものですね。